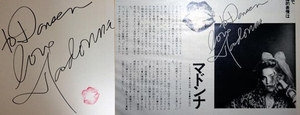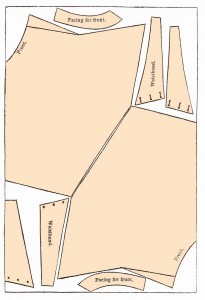男子專科(1979年2月号)より
なりふりかまった青春時代
昭和28年、全学連の集会で私は紺のダブルの背広を着て壇上に立っていた。学生運動家といえば皆ボロボロの学生服を着て、その袖口をこすった鼻汁でビカビカに光らせ、ヨレヨレのレインコートをひっかけていたころだ。
翌年、撮影所にはいったら、助監督たちは皆ジャンパーを着、ハンチングをかぶっていた。ああいう格好をしなきゃいけないのかと思い、二本ばかりやってみたがどうにもしっくりせず、すぐ脱ぎ捨てた。その頃はやりの黒のマンボズボンをはき、グレー・フラノの上着を着てリボン・タイを結んだ。セットは汚れるという理由でジャンパーを着ている先輩は呆れ、ひんしゅくした。
夏は白の半袖シャツ、白のトレパンで、ストップ・ウォッチをさげる紐だけが赤だった。その頃、監督候補生としてもっとも有望といわれていた某先輩は汚れ放題の進駐軍のジャンパーを着ていた。仕事に一生懸命で、なりふりなんかかまっていられないというのだうか。それは彼らなりのダンディズムであったかもしれないが、私は自分の格好さえかまえない奴にいい映画なんか撮れるものかと、心の中で冷笑していた。
今年、評判になったテレビの防衛論争に私ほ麻の白絣の着物で出た。それは、日本人にふたたび軍服を着せようとしている奴らへの私のプロテストであった。
要するに私は昔も今も制服を着せられることが絶対にいやなのである。制服だけでなく、学生運動家なら運動家らしい服装、助監督なら助監督らしい服装というものをどうしても受けつけられなかったのである。
それは私が戦争中に制服を着せられた、ほとんど軍服に近い制服を着せられた少年であったからかもしれない。しかし、当時の少年の大多数は制服を素直に受け入れ、そのまま制服好きになり、今もドブ鼠色の背広を着て会社へ通っている。
とすれば私の制服嫌いはもっと根の深いものなのだろう。
らしさへの反逆
父が写真好きだったせいで、子どもの頃の写真がたくさん残っているが、一枚得意満面の写真がある。5歳ぐらいだろうか、背広を着てハンチングをかぶっている。昭和10年頃の日本の田舎としては異例のおしゃれだったろう。そのことを意識したから得意だったのだろうと思う。一介の官吏にすぎなかった父が裕福だったはずはない。しかし、父と母は我が子に似合う服装をさせ、そのことを喜びとする心のゆとりは持っていたのだろう。私はそのことを感謝している。
しかし、まもなく支那事変が始まった。父は病死し、私たちは母の実家のある京都へ移った。それまで住入でいた瀬戸内海にくらべ京都の空は暗かった。その下で制服しか着られない日々が続いた。私は制服は自分に似合わないと感じつづけた。小学校4年で眼鏡をかけるようになってからは特にそうだった。
そんな私にとって敗戦は解放だった。すくなくとも服装のうえでは解放だった。
私はクラスでいちばん先に髪を伸ばした。進駐軍の将校の古着を手に入れて仕立て直しジャンパーとして着て、高校時代を過ごした。将校、というところに意味がある。同じく進駐軍の毛布を黒く染めてハーフコートにした。そいつはいささか重かったが格好いいつもりだった。その上にマフラーをなびかせて大学へ通った。
全学連大会で着たダブルの背広をふくめ、けっして金がありあまって手に入れたわけではない。でも、青春はなんらかの自己表現をしなきゃ生きていけないじゃないか。その自己表現をありきたりの型でするのはいやだった。学生運動なら学生運動のパターンでするのはいやだった。だから私は服装で異を唱えただけでなく、当時の学生運動家ならほとんど皆が入党した日本共産党へもはいらなかった。精神の制服を着ることもまた、いやだったのである。
ついでに言えば、その学生時代から今日まで一貫して、私は家では着物を着ている。楽だということもあり、自分に似合うということもある。というより、洋服の普段着は私に似合わないと思っているからである。
そういう意味では、私の服装に対する哲学は、似合うものを着るというより、似合わないものは着ないという防衛的なものである。
3年ばかり前、ある高名なカレー・メーカーからテレビのコマーシャルに出てくれという話があった。家内と一緒ということだっがあくまで私が主で、契約金は1千万円ということだった。私の友人には佐藤慶のように俳優はコマーシャルに出てはならないという信念の持ち主もいるので叱られると思ったが、お金もほしかったので出ることにした。
家庭でくつろいでカレーを食べてるところだというので着物を着るつもりでいたら洋服にしてくれという。着物姿をお見せするのも悪くない。ディレクターもそのほうがいいというのだが、ポリシーのはっきりしている会社で、どうしても洋服に固執した。しかたがないので行きつけの洋服屋でつくらせ、テスト・フィルムまで撮った。しかし、どうしてもいやなのである。結局、すでに振り込まれていた1千万円をお返しして、この話はなかったことにしてもらった。
・・・次回更新に続く