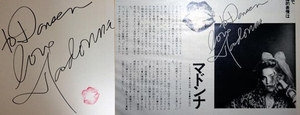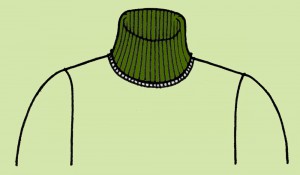日本でそもそも「◯◯族」という言葉が使われた最初は、1948(昭和23)年の「斜陽族」からだという。太宰治の小説『斜陽』(1947年12月刊)から出たもので、第2次世界大戦後に没落した上流階級の人たちをそう呼んでおり、これは48年6月、太宰治が玉川上水で心中事件を起こしたところから、一気に広がったものだ。これが51年には会社の車を乗り回し、高級料亭で遊びまくる「社用族」というように転用されるようになるが、日本における「族」の歴史なんてそんなものだったのだ。いずれもファッションとはなんの関係もないが、徒党を組んでとんでもないことをやらかす若者集団という意味では、やはり「太陽族」を日本の「族」の元祖としなければならないだろう。そして、そのリーダーと目された青年こそ石原慎太郎氏(元・東京都知事)であったのだ。
ファンキー族&ダンモ族
50~60年代「ビート族」1959~1963
マイルス・デイヴィスやアート・ブレーキーなどのモダンジャズ(ファンキージャズ、ダンモとも俗称)を専門に聴かせる喫茶店にたむろして、精神安定剤や睡眠薬に酔い痴れる若者たち。これを日本版ビートニクスの意味で「ビート族」と呼んだ。本来のビートニクスはJ・ケルアックやA・ギンズバーグなどビート詩人たちの思想に共鳴する実存主義の若者たちを指し、1950年代後半のアメリカで生まれた一種の芸術運動をいうが、日本ではその風俗的な面だけが独り歩きしてこのような不良を意味するようになった。ビートニクスというのはビート(打ちひしがれた)と57年10月に打ち上げられた世界初の人工衛星、ソ連の「スプートニク」を合わせた造語で、つまりはビート・ジェネレーション(敗北の世代)と呼ばれる当時の若者たちを総称している。日本のビート族はこうした思想とは関係なく、ただモダンジャズに熱中して世間から逃避しようとする傾向だけが目立ち、「ファンキー族」や「ダンモ族」とも呼ばれた。