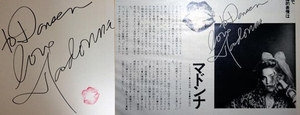一着のレインコートをめぐる小説風断片(9)
4時35分、彼は片手に小銭を握り、レジスターの脇の赤電話に向かう、そしてダイヤルを回す。何百回と回してきたナンバーなのに、まるでとりかえしかつかないほどもつれてしまった数字のかたまりのような気がする。何回かベルが鳴るあいだ、彼は胸のポケットから煙草を取り出し、湿っぽい紙マッチで火を点ける。煙草までがどこかで湿ってしまったような味がした。
ベルは沈黙の中で際限なく鳴りつづける。7回、8回、彼はべルの数を数えながら自分の足もとを眺める。朝にはしっくりに足に馴染んでいたキャメルのデザート・ブーツは雨に濡れて黒く染まり、洗ったばかりのコーデュロイのズボンはすでに膝が抜けかけていた。まるで他人の足みたいじゃないか。
11回、12回・・・・・・
いや、結局はこれが俺の足なんだ。俺はこの足で、これからどれだけの距離を歩かなきゃならないんだろう。
15回までベルの音を数えてから、彼はそっと受話器を置く。
・・・次回更新に続く