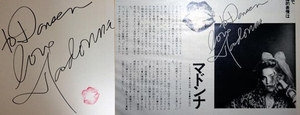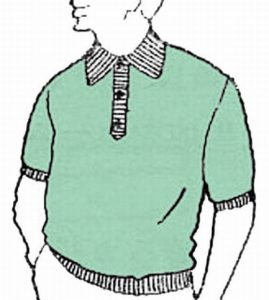一着のレインコートをめぐる小説風断片(10)
通りではまだ雨が降りつづけていた。弱まるわけではなく、かといって強くなるわけでもない。のばされた思い出のように、雨はこのまま永遠に降り続のくかもしれない。
まるで水族館の中にいるようだな。彼はふと、子供の頃に何度も通った近所の水族館の光景を想い浮かべる。人通りの途切れた暗い水族館の通路だ。冷やりとした水槽のガラス窓に何度も頬を押しつけてみたっけ・・・・・・。
信号が青に変わり、彼は歩き始める。傘はどこかに置き忘れてしまったようだった。両手はまるで呪縛にかけられたように、コートのポケットの中にすっぽりと収められていた。不思議だ、よりによって雨の日に傘を忘れちまうなんて。
街は芯までぐっしょりと濡れていた。そして歩くにつれて彼のレインコートも黒みを帯びていくようだった。草原のまんなかに辿りつく前に、俺の体はきっとこわばって、このまま雨の街に閉じこめられてしまうのかもしれない、と彼は思う。
信号が赤に変わり、彼は立ち止まって口に煙草をくわえる。迷路のようなコートのポケットから紙マッチを取り出すまでに、ずいぶん長い時間がかかった。
・・・了