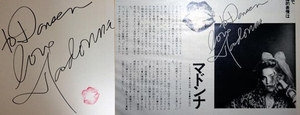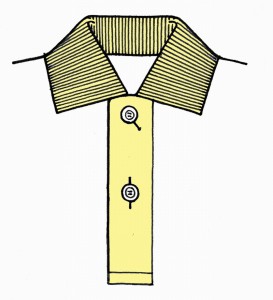男子專科 1986年4月号 NO.265 より
カイロの紫のバラ
「また来てくれたんだね」と映画の主人公がスクリーンを脱け出して観客席の娘の前に立った
それまでウディ・アレンの映画を見たことがなかったわけではない。『カジノ・ロワイヤル』や『スリーパー』で知っていた彼はアクが強かったし、『ボギー!俺も男だ』の彼からは”哲学”すら感じられた。そして、『アニー・ホール』ではエスプリに富んだ乾いた笑いに堪能させられもした。この時までは、ウディ・アレンの人物像というものも、なんとか見えていたような気がする。
しかし、『インテリア』となるとちょっと話しが別だ。それは私が単なる観客としてではなく、宣伝担当者としてこの映画に出会ったということもあるだろう。それにしても、私にはこの映画における彼の変貌が信じられなかった。グルーチョ・マルクスほどの毒はないにしても、必ずつきまとっていた”笑い”がまったくないだけではなく、ヴィスコンティを思わせる重厚で格調の高い正統的なドラマに仕上がっていたのだから。
宣伝のほうはこの変貌と、彼の持つ都会的なセンスをクローズ・アップすることで、なんとか成功させることができたものの、私のウディ・アレン感は大きく変わってしまった。
『インテリア』以後、彼の作風は昔のニューヨーク臭い乾いた笑いを持つものに戻ったように見える。だが、それ以降の映画を見る時、私はどうしてもカマエてしまうようになってしまった。それはウディ・アレンがどんな人間なのか、なにを考えているのか、あれ以降まったく見えなくなってしまったからだ。それでもヴィスコンティに憧れを持つ部分も含め、彼の映画が気になってならない。大部分の彼のファンもそうだろう。好き・嫌いではなく、ウディ・アレンの感情は都会に生きる我々には共感できるものなのだから。