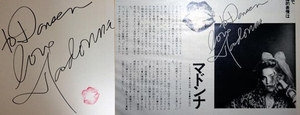男子專科 1986年5月号 NO.266 より
キャバレー
ジャズのすすり泣き抜きには生まれなかった原作は、ジャズと50年代の空気なしでは語れない映画になった
日本映画が好きな私にも、そのダサさが鼻につくということがある。だがソレは決して俳優の演技といったものではない。気の利いた科白やムード、そうしたものがほとんどの日本映画には欠如しているのだ。あったとしても、変に意識しすぎて浮き上がったものになっていることが多い。その場に合った科白なりムードを持った邦画となると、本当にその数は少なくなってしまう。
この原因は、ひとつには脚本にあるのではないだろうか。酒落た欧来の映画などでは、ストーリー・ライターとダイアローグ・ライターが別々の人間に書かれているケースが多い。この方式ならばストーリー・ライターは物語の進行だけに気を使えば良いのでかなり凝った場面の設定ができるし、ダイアローグ・ライターはその場面にふさわしい科白を考えてさえいれば良いというわけだ。
ところが日本映画では、こうした方法がとられることはまずない。複数のシナリオ・ライターによって書かれた脚本の場合でも、ストーリーとダイアローグとを分けて書かれるということはない。ストーリーも、科白も、ひとりのライターがすべてを書かなければならないとすると、これは大変な仕事だ。不可能と言ってもいいだろう。例外的に可能なのはよほど腕の立つライターが、よほど緻密に練り上げられた原作と出逢って、脚本も原作も十分にわかっている監督によって製作される映画ぐらいだ。『キャバレー』はちょうどそうした具合に生まれた、日本映画としては極めて例外的なムーディな映画といえる。